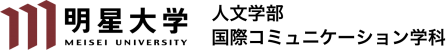フィールドワーク、現地に行けなくなったからもしや授業そのものが中止になっているのでは?と思われる方も多いかもしれない昨今のこの状況。 いえいえ、そんなことはありません。国際コミュニケーション学科では、『行けない』を『あえて行かない』←笑、に発想転換し、本来研究すべき “フィールド” を、現地学生を巻き込んで一緒にそれぞれの環境を研究、共にネット上で成果発表を行うという授業に切り替え、フィールドワーク授業を続行中。 後期は、大連にある遼寧師範大学の日本語学科の有志学生にも参加してもらい、各チームに分かれて、お互いの環境について研究→分析→発表をし合い、文化交流を深めています。 好奇心旺盛な大学生達、お互いの文化の違いについて、興味津々なこと、たくさんありますよね?世界観、家族観、結婚観、金銭観……。 そこでまずは学生達と同世代のYoutuberによる、文化の相違についてのご紹介。

■ 日本では仕事中に携帯をやってはいけないというルールがありますが、中国では携帯をやることが仕事をさぼっているという考え方と同じにはならないので、特に仕事中に携帯をいじることを咎められることはありません。
趙先生:「これは大きな違いですね。日本では仕事に対して非常にシビアですが、中国ではみんなぼちぼち働いて、あとは自分たちの日常を楽しもうという考えがものすごく強いですから、仕事が絶対1番の優先順位にないのかもしれません。どうですか?」遼寧師範大学の学生:「確かに。日本のニュース映像はスーツで駅に向かって歩く人がよく映し出されているみたいですが、中国ではあれもあんまりないですよ」学科の学生:「世界中、仕事は絶対にスーツだと思ってた!」
■ 仲間と食事に行く時、日本では割り勘が普通ですが、中国では『誘った人が全員分を払う』のが普通。
趙先生:「そうなんですよ、私も初めて日本の大学で働き始めた時、教員が1万円を支払い、あとは学生が負担したのを見て、財布のヒモが固いのかとずっと勘違いしていたんです。よく分からなかったので、私はゼミ生達の分を自分が出してたのですが、それをしない(割り勘にする)というのは、日本のモノの物価が高いというのも理由にあるのかもしれませんね」するとすかさず、遼寧師範大学の学生:「先生、デートの時は、男性が支払いますよ。これは日本も中国も一緒ですよね」学科の学生:「日本は最近は割り勘も増えてますが、メインのところを男性が払って、お茶などを女性が払うって形もありますね」
■ 中国では恋人になると一日の中でも常時きめ細やかに連絡を取り合うので、プライベートの時間が格段に無くなります。
学科の学生:「え〜っ」笑 「ただでさえ忙しい毎日で、自由時間を恋人にほとんど捧げなくちゃいけないのは、ちょっと引くなあ……笑」遼寧大学の学生:「いいんじゃない? 恋人なんだもの」


■ 日本では小中高校生の恋愛は自由ですが、中国ではまさかの禁止!?
趙先生:「私が小さい頃はそうでした。でも今は時代が変わったかな?」遼寧大学の学生:「そうですね、今はそこまで厳しくはないかも」学科の学生:「私たちには考えられないなあ……笑」
■ コミュニケーションの方法を文字にするか、音声にするかも、中国と日本では大きく違います。
遼寧大学の学生:「そう。私たちは基本、音声でコミュニケーションするから、メッセージも文字ではなく、音声吹き込みで送るのが普通です」趙先生:「ですよね。日本では文字で相手に伝えるのがほぼ100%かと思うのですが、中国は文字を打つ時間がもったいない(?)から、音声で吹き込む。そして返事は電話で、というのが普通ですね」学科の学生:「コミュニケーションも、目を使うか、耳を使うか、優先させる機能が随分違うんだなあ。面白いなあ」

自分でネット上で海外の人とコンタクトしようと思っても、なかなか思い切れないところ、ならば、そんな学生の好奇心を学科が中心となって『場づくり』をする、それが今のフィールドワークのやり方。「そうなんです。大学がこれまで培ってきた関係性において、海外の他大学と時間を合わせて合同で何かをやることができるようになった。それをプロデュースするのが私の仕事です」と趙先生。
なんとなく分かっているようでいて、こうしてお互いに同じ場所で語り合ってみれば、私たちを楽しませてくれる細やかな異文化ギャップエピソードが、実にたくさん!
これらの話がチーム毎にまとめられ、正式にプレゼンテーションされるのは12月。それが完成すれば、これまで学科でも類を見ない、ネット上での2大学合同レポートがまとまることになります。 どんなレポートに昇華していくか、どうぞお楽しみに⭐︎