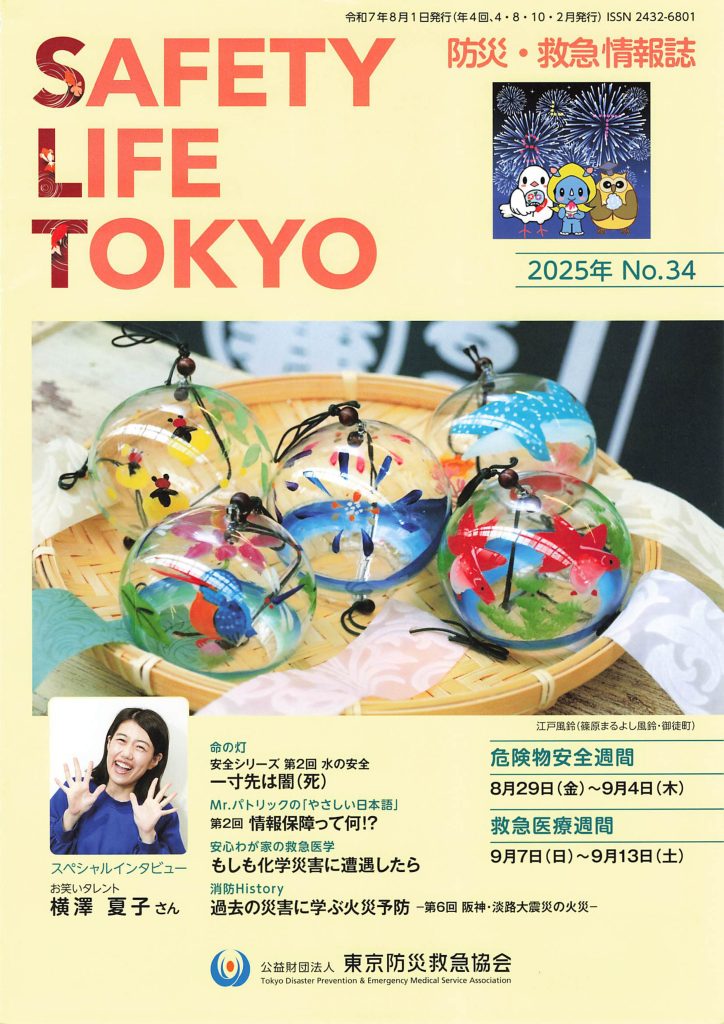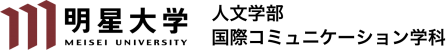国際コミュニケーション学科の教員は、大学構内にとどまらない→実社会での活動にも力を入れている先生が多く在籍しています。その1人が、現在国内フィールドワークの企画立ち上げに奔走している菊池哲佳(きくちあきよし)先生。菊池先生は、仙台国際交流協会での仕事を皮切りに、東日本大震災で仙台市が作った『災害多言語支援センター』の運営に携わり、この4月から学科には教員として加わられました。
菊池先生の実社会での活動テリトリーは、『質の良い多文化社会』を作っていくためにどうすれば良いか。先生はご自身の経験から『外国人住民向けの情報保障』の必要性を感じ、外国人住民に寄り添った『やさしい日本語』を展開。断絶が生まれないよう国籍を超えたコミュニケーションを深め、『やさしい日本語』マインドで有事の時に『助け合える』関係を築く、それが菊池先生のアプローチ。

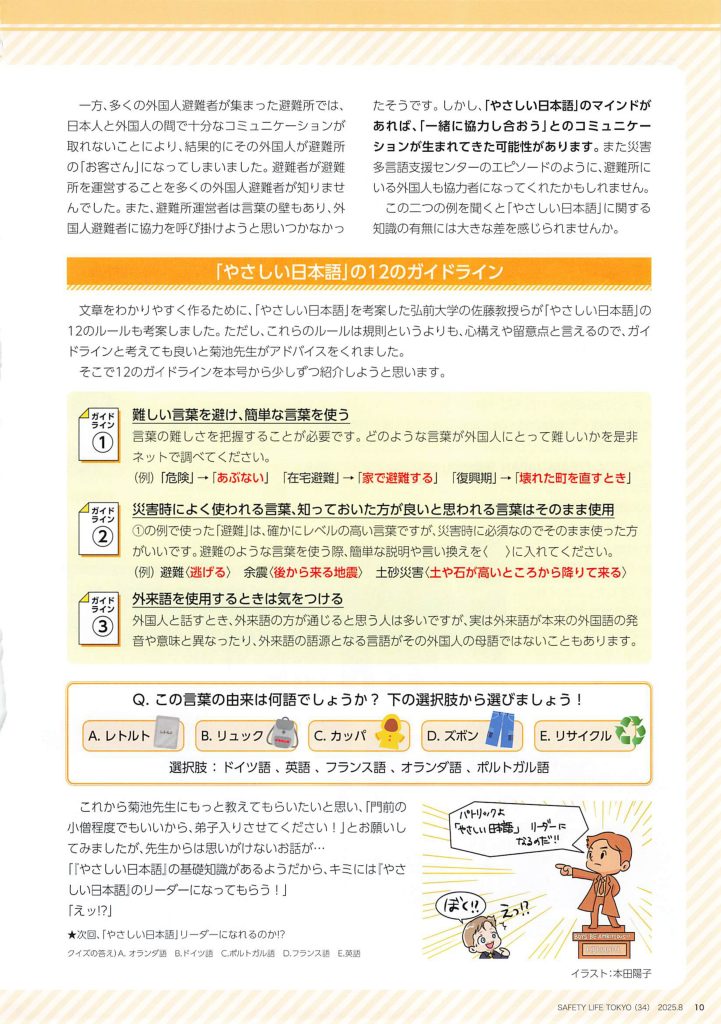
昨今の国内における世論にみられるような“ 切る” は簡単だけれど、あえてそれはやらない。で、手間も時間も努力も必要な方法を採る→『やさしい日本語』を通じて、お互いの関係性を『育てる』。そんな挑戦(社会実装)を先生はしています。
ニッチなエリアでのスペシャリストが在籍する国際コミュニケーション学科。2040年には10人に1人が外国人住民になるだろうと言われています。そんな未来に興味があるみなさん、ぜひ学科の菊池先生の授業を受けてみてくださいね。