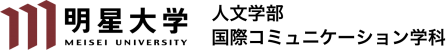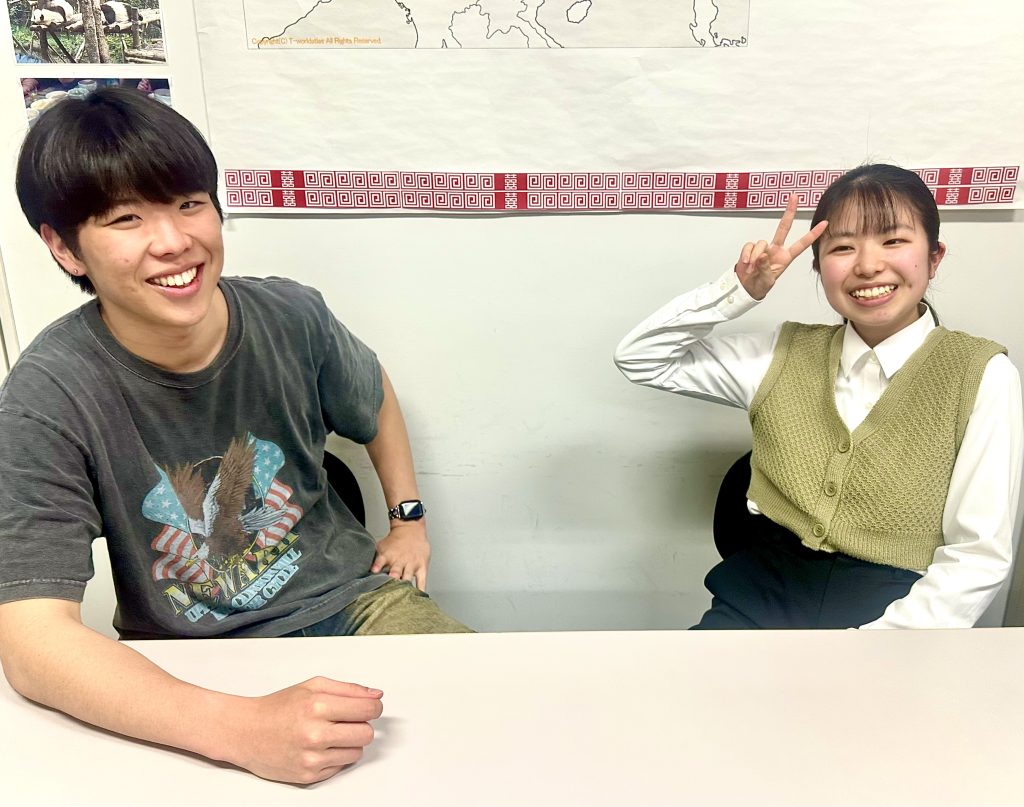
スタッフ「お二人はどういう経緯で学科へ来てくれたの?」
Miss「私は、授業の中でフィールドワークをやってて、いろいろ行けるってのが大きかったな。小さな頃から学校がめっちゃ好きで、高三の時にコロナ自粛で学校へ行けなくなった時に、自分にとって学校は第二の居場所だって悟り、先生を目指そうって思ったんです。ならば『教育の明星』じゃん!笑、と。で、高校の先生に相談したら、教育学部じゃなくて人文学部に行くのもあり、それならいろんな経験もできて教職も取れるからって教えてもらったんです。あとは他学科との関わりも深いってのもポイント高かった!」
Mr「俺は元々言語好きだから、単純に英語やってみたい、カッコイイじゃん!さらには、フィールドワーク行ってみたい!多言語学べるじゃんってのが動悸。今でもそうなんだけど、どちらかというと、鉛筆片手にカリカリと机に向かって勉強するより+考えるよりも先に行動する方が得意なタイプ。結論から言うと、机を離れた学びが多いこの学科の教育方針は俺にはめっちゃ合っていて、本当に国コミで良かった!と心から思ってます。実は英語は入学してしばらくしてから挫折して、今は韓国語をやってるんだけどね」
スタッフ「えー?? それだけいろんなことがしっかり話ができて、挫折を経験してるんだ?」
Mr「学科に入ってみたらそれなりに英語ができる人もいたから、自分としては挫折、笑。 でもそのあと韓国に興味が湧き、韓国語やってみたら語順が日本語と一緒だったから意外とすんなりできて、今ハマりまくってます」

スタッフ「どうやって勉強してるの?」
Mr 「大学で授業を取ってる他、言語を交換できるおしゃべりアプリも使ってます。それが結構勉強になるんですよ。とにかくまずは使ってみよう、喋ってみようスタイル、笑」
スタッフ「かしこまったやり方でない勉強方法もあるってことだよね?」
Mr 「そう。俺にはそういう “感覚的アプローチ” から入る勉強法の方が合ってたみたいです。国際コミュニケーション学科の学生って、めっちゃよく喋る人が多いんですよ。しかも授業はテーマを与えられて、自分でそれを調べてパワポに落とし込んで、みんなの前で喋る。そうすると、たくさんの人を前に喋っている間に、また自分の中にその学びがきちんと定着していくんですよね。俺は自分が興味あることならめっちゃやれるから、与えられるテーマの幅が細かすぎないのもなおよかった。学科の授業って、常に人前で話す訓練をしている感じだから、そりゃコミュニケーションは上手くなるよ。」

Miss 「授業で発表してる間にもうもう一度学べる感覚ってわかる! モヤッとした言語化できてないものが、そういう作業を通じて頭の中できちんと整理されていくんだよね。学科にいると知らない人と話すのに抵抗がなくなるってのもよくわかる!
国際コミュニケーション学科の場合、個々の先生たちが扱っているテーマも幅が広いから、授業の選び方によっては自分の幅がかなり広がると感じてる。自分だけで物事を決めると、案外 “やりたいこと” ってある程度範囲が決まってしまってる。それを個性的な先生たちが、いろんな世界の面白さを見せてくれるから、気づいたらそれに巻き込まれて自分も色々面白い体験をしちゃってるという感じです。自分では発掘しきれなかった自分を見つけられる、とも言える。英語言語学、アニメ学、多言語主義の専門家の先生が揃っているほか、フィールドワークはうまくすれば4大陸に行けちゃう♪」
スタッフ「え?4大陸?」
Miss 「私は、1年生の時には海外からたくさんのボランティアが来る明星サマースクール@日本、2年次にアフリカのザンジバル、3年次でマレーシア、4年生の今はこれからポーランドへ行きます。それぞれの場所で、日本とは全く違う “ナニカ” を見て、自分の幅はかなり広がりました。小さなことだけど、ドリンク頼んでも提供に20分くらいかかるザンジバルでは、少なくともお客様は神様ではないんだな、店員さんと対等な関係なんだなと学んだし、マレーシアでも水上生活集落という現場から、国際関係を学びました。近い将来子供達に教える仕事についた時に、そこでリアルに見たものをたくさん伝えていきたい。そういう意味では授業という形で現場に行けたのはラッキーだったと思います。訪問先はどこも人間関係の絆が強くて、そこは感動したなあ。ザンジバルなんて助け合いで社会が成立していると感じました」

Mr 「俺はマルタとトルコに行きました。フィールドワークは行く前に自分が興味持ったことを調べて、みんなの前で発表するというタスクがあるのですが、行ってみればその事前学習がいざ現地に行った時にいろんな横糸になって繋がって、とても面白かったです。トルコでの朝、不思議な音が聞こえてきたら、それはアザーン(イスラム教のお祈りの音)だな、とか、マルタの街角で見るマークにはこんな意味があるんだな、とか。やっぱり体動かして活きた学習を授業の中でできるのは、本当に性に合ってた。韓国が好きすぎて、8月には1ヶ月提携校のキョンヒ大学に留学するのですが、いくら俺が元々考えるより行動が先というタイプだったにしても、そんな大胆なことをできるほど成長するとは自分でもちょっと驚きです。今なら他大学を勧められたとしても、明星の国際コミュニケーションに来ちゃうな」
スタッフ「涙。そんな本音、うれしすぎじゃないですかあ!なんなんだろうね、学科の何がよそと違うんだろ?」
Miss 「自分次第でいろんなことができるチャンスがたくさん用意されてるとこだと思います。授業が『板書の書き写し』で終わらないところ」
Mr 「そうそう。自分にとっての新しい窓口が、たくさん口を開いて待ってる!ってとこ。その新しい窓口に夢中になってたら、あっという間に4年が経ってた。『 ただの “勉学” 以外のナニカ』を習得してぐっと成長していることを実感してます。これは総合大学ならではの良さですが、マルタに行った時も、俺にとっては異世界の仲間ができた。彼らは情報学科の学生なのですが、マルタのフィールドワークでは、発想も思考回路もまるで違う技術色の濃い人種と一緒になってプロジェクトを組むんです。これって、一般社会と一緒ですよね、全然タイプの違う者同士でお互いの利点を生かしながら一つの目標を達成するって。そりゃあ、難しいことだらけなんです。コミュニケーション学科内の学生同士のコミュニケーションが彼らには通用しない。だから、それがなぜ?どうして?どうすれば?と考える。これが実は自分にとっての何よりの成長のチャンス。分野が違う人と一緒に何かを作るのは大変ですよ、でもそれができたらもっと大きな成長ご褒美が自分にやってくる。そういうチャンスがあるという意味で、学科はよかった」

Miss 「私もあるな、それ。ゼミで、資本主義 VS 脱成長 でディベートをしたんです。これって時代の最先端の話題。答えは結局でないかもだけれど、私たちが知りうる限りの&体験しうる限りの情報を持ち寄って、全員で答えを出すんです。結局その時は、“資産のコモン化” を解決の糸口として据えたのですが、フェアトレードカフェ然り、こんな社会に直結した時代性にマッチした話題をゼミ生で議論できる、しかもその議論が全て、学生の自主性に基づいて行われているという意味では、授業も非常に有意義です」
スタッフ「なんかお二人の将来が楽しみになってきました。自分の歩く道を学科在学中に見つけてもらえたことが、何よりもうれしいです」
Miss 「自分が大学でしてもらったように、一方的に大上段に構えて教える教員ではなく、生徒と一緒に成長していく教員を目指します」
Mr 「俺は一旦就職する予定ですが、そのあとは韓国にワーキングホリデーに行って、ゆくゆくは向こうで暮らしてみたいなと思ってます」
==================
学科の卒業生の進路は実にさまざま。公務員から教員、国内企業から海外のホテルまで。
そんな多様性豊かなカッコイイ先輩たち&個性豊かな教員たちが、オープンキャンパスで待ってます。
W(ダブル)ナカムラ先輩に会いたい人は、@meiseiinter を見てね☆