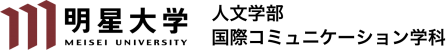菊地ゼミの学生が企画→プロデュースを手掛けた【Africafe(助け合い、支え合い、輝いて生きる。そんなアフリカの素晴らしさを伝えるイベント)】。その一環として、12/13(金)には、学科や大学を超えた来場者もお招きし、元学科生にお話をしていただくトークイベントが行われました。
この日登壇したのは、元学科生で、現在は車椅子ハンドボール界を牽引する日本代表・諸岡晋之助選手。諸岡選手は国際コミュニケーション学科に入学、ハンドボール部に属して活躍する傍ら、ザンジバル(タンザニア)フィールドワークにも参加。その後、交通事故に遭い生と死の境をさまようも、長期間入院を経て一命をとりとめ、その後は車椅子ハンドボールの選手として復活。事故を通して自分と対峙して得た見事なまでの人生の歩き方、考え方、モノの見方を、来場者にド直球の本音で語ってくれました。
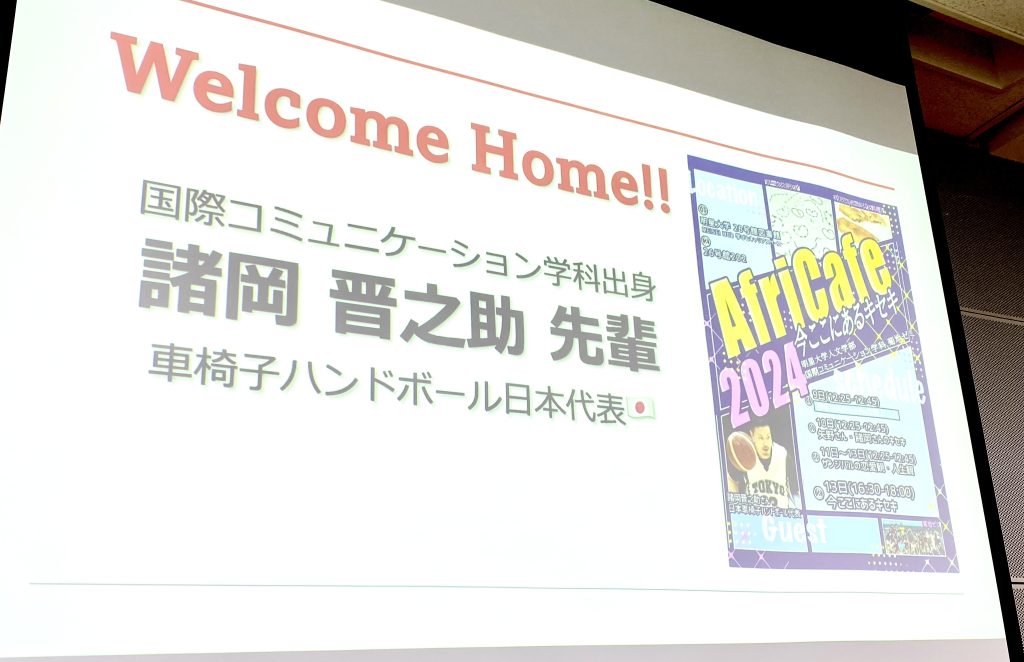
▪️ 諸岡さんは小さな頃からスポーツ少年だったのですか?
「そうですね、大好きでした。高3の時にはインターハイを目指していました。両親とも水泳の選手というのも影響していると思うんですが、スポーツが好きというよりもむしろ、“挑戦” とか “勝負” が好きなんだと思います」
▪️ 学生時代、ザンジバルに行った時に何をどう感じられましたか?
「僕はずっと体育会系のスポーツの中だけで育ってきていたので、ザンジバルに行って一番最初に思ったことは『オレって随分小さな世界に生きてたんだなあ』でした。競技スポーツにはルールがあって、その中で戦う。ザンジバルに行ったらそれらが取れて『自由になった』って思いました。世界は実は自由で、何でもできる可能性を秘めているんだな、と。シャワーの栓をひねったら、出てきたのはいきなりサビだらけの赤い水!笑 みんなもそれ、体験したんだよね? でもザンジバルにいると、『それも、ま、いっか!』って思えたのが本当に不思議でした。市場を歩いていた時だって、ずっと俺の後ろを勝手についてきてたヤツ(現地人)がいて、最後『ついてきてあげたんだから、お金くれ!』だもんな、笑。それってアリ??笑 けど逆に、この世界はそんなことができるくらい、本当は自由なんだ、と気付かされたというか。暮らしは不便なはずなのに、あの自由さはなんなんだろうと考えましたね」

▪️ そんな諸岡さんが大学2年生の時に交通事故に遭われたんですよね?
「いや、あの時は本当に死にかけました。みなさん、今日と同じ明日が来るって、どっかで思ってますよね? そうじゃないんですよ、本当は。今日と明日が来ない可能性は結構あるんですよ。笑 実際、俺がそれを体験してますから。明日がないかもしれないって思ったら、やりたいことやれて死ねたら本望だなと思うようになって。好きなことを存分にやって死ねたらいいよな、と。好きなことをとことん追求できるチャンスが、生きていればまだある! 俺の場合はスポーツとか、ね!」
▪️ どうやってまた競技に復活したんですか?
「療養中ベッドにいた時に、友人に『車椅子でできるスポーツあるよ』って勧められたのがきっかけです。よく『落ち込まなかったんですか?』と訊かれるんだけど、俺の場合は、落ち込むというよりも、『死ななくて良かった!!』って考えた。死ななければまだいろんなことができるから。ある意味、スポーツに救われている部分もあるのかもしれない。車椅子ハンドボールも、俺より上手な人がいるんだー!と知って、なら挑戦しようか、と。今はハッキリ言ってしまうと『俺より上手な人は誰もいません!』笑」
「よく『苦しかったことはないんですか?』と訊かれるんだけど、自分の気持ちに素直になって言っても、実は『苦しかったことって、本当にナイ!!』んです。もちろんその場で苦しいと思うことはなくはないです。でも基本、それに向かって “挑戦” することはできる。そのハードルは高くない。“ 挑戦 ” すれば良い。“ 挑み続ける ” ってめちゃ楽しいことなんですよ!」

▪️ 諸岡さんにとって、幸せってなんですか?
「いきなり難しい質問、きたね。笑 みなさんにとってはなんですか? 俺にとってはなんだろ……。仲のいい友達と、美味しいご飯を食べている時、かな。そうそう、幸せって、実は絶対的なものじゃなくて、それに自分が気づけるかどうかって話だと思うんだよね。幸せとはどこかにあるはずと追いかけるものではなく、すでにたくさん身近に転がっている幸せに、自分自身が気づけるかどうか。要は “心の感度” を高めておくことが幸せに直結するってこと。“ 心の感度 ” が低いと、どれだけの幸せがあっても気づけない。から“ 心の感度 ” は高めておいた方がいいよね、常に」
▪️ 諸岡さんにとって、今までで一番幸福だったことってなんですか?
「……(じっくりと熟考した後)今、ここでみなさんに自分の体験を話せていること。……俺は常に、今が一番幸せって思ってるから」(会場には自然に拍手が湧き起こりました。来場者の心に何かが痛烈に刺さった瞬間)「1人でも多くの人に俺の話を役に立ててもらえるなら、それは本望です」
▪️ 教えてください、諸岡さんのそのポジティブさは生まれつきなんですか?
「……(しばらく考えて)まあそうかもしれないねえ。小さな頃の家庭も相当厳しかったから、『どうやったら生き残れるか?』みたいなのをゲーム仕立てにして楽しんでいたようなところがありました。どうせ勝負するなら、負けたくないしね」

▪️ 僕にも教えてください、僕は悩める大学生です。思考に捉われて行動ができなくなったり、落ち込んだり。アドバイス、ください。
「まずやって欲しいのは、『とことん自分と向き合うこと!』。しっかり自分を見つめ直す。そして自分を理解する。そこから自分を受け入れる。受け入れるのは “そのままの自分” 。どれだけダメと思えても、飾り気のない、余計なものがついてない “素の自分” を、まずはしっかりと受け入れる。で、自分をちゃんと見つめ直すと、自分が腹の底から “好きなこと” が見えてくる。そしたら、まずはその自分が “好きなこと” を、何かを確立できるくらいまで、徹底的に頑張って欲しい」
「一つ言っておくと、俺は “努力” は好きじゃないんだよ。でも “頑張る” は大事。それが毎日の自分の成長につながるから。俺はね、1日に手を抜いたことがないんだよね。もちろんうまくいかない日もあるよ。けどそれは次への糧と捉えて、とりあえず “できるところまで頑張る” 。例え、失敗したかな?と思うようなことがあっても、気にしない。なぜなら、その時に失敗したと思うことがあったとしても、長期ではそれは失敗じゃなくなるから。つまり、失敗って、存在しないんだよ。これ、ほんと。そして1日1日、手を抜かない日を、自分の人生に少しずつ増やしていくんだ。『今日も1日頑張れたな』って思う日を自分で増やしていく」
「その時大事なことがもう一つあってね。それはその “頑張る” を “義務” には決してしないこと。 “義務” にすると苦しくなるからね、あくまで “これはゲームだ” って楽しみながらやる。これは自分のコントロールにもつながるんだけどね、みなさんは今19-22歳でしょ、これからどんどんその感覚が分かるようになっていくよ、大丈夫」

▪️ 大学卒業後に、社会人になることが不安で仕方ないです。道を考えるときのコツなどを教えてください。
「まず一つ。先に言ったように、今は自分と徹底的に向き合って、余計な外の声などを削ぎ落とし、自分の “好きなこと” “やりたいこと” をしっかり把握する。これを仮に “自分軸” と言おう。学生と社会人の決定的な違いは、学生はともすれば “自分軸” だけで十分に生きられる。けれど、卒業するともう一つ(二つめ)の軸が必要になる。それはなんだと思う? それは “社会軸” 。言い換えれば、“ 社会があなたに求めていること” 。社会に還元していけること、もしくは社会的な意義を持つこと、をやること。この2つの軸は一致しない場合が多い。前者は “好きなこと” “やりたいこと” 。後者は “社会に求められていること” “やらなきゃいけないこと”。そしてこの後者が自分にとって何かをハッキリさせるために、実は前者を学生のうちにハッキリと自分で分かっておくことがとても重要だと、俺は考えています」
「社会に求められることをやりつつ、同時に自分がやりたいことを求める。複雑な方程式みたいだよね。この2軸をうまく成立させていくためには、それなりの戦略も必要で。でもさ、みなさん、それを考えていく挑戦が、人生の醍醐味であり、面白みであるとは思いませんか?」
▪️ 最後に諸岡さんの将来を教えてください
「今の自分が座標軸のどこにいるかをしっかり分かっていれば、今自分がまだやれていないことでやりたいことはたくさん見えてきます。僕の中の当面の目標は、車椅子ハンドボールの世界で、後進を育てていくこと。なぜかって? 現状、俺より上手な選手が他にいない(これ以上の上がない)から、笑。目標は自ずと、まだやっていないこと、に向かうもんね」
諸岡さんのお話に、聴講者全員がぐいぐいと引きずり込まれていった1時間半。車椅子での、ウルトラCな軽やかな動き方まで会場で披露してくださり、全員が釘付けの拍手喝采!パリッとした出立ち、率直な思い、チャレンジングなマインド。迷っても速攻で答えを出していける経験値の高さ。どれをとっても、ヒトとしての圧倒的な存在感が感じられる諸岡さんでした。
====================================
最後に菊地ゼミのゼミ長から一言。
「今日はみなさん、ご来場ありがとうございました。(中略)どうでしょうか?みなさんは自分たちの日常の “あるもの” に気付けているでしょうか? その“あるもの” に感謝できているでしょうか? アフリカには『ウブントゥ』という言葉があります。簡単に言うと、『あなたたちがいるから私がいる』。つまり自分の存在は他者との繋がりによって成り立っているという考え方です。この言葉には自分が持っているものを惜しみなく他者に分け与える精神が込められています。それは実は他人のためではなく、結果的に自分の暮らしも豊かにしていく力です」

「実は私たちの周りにも、日々の些細な幸せがたくさんあります。それを当然のものとして考えてしまいがちですが、忙しい日々の中で、誰かの『ありがとう』の一言にどれほどの価値があるか、考えたことがあるでしょうか? 友人との会話や、家族との何気ない時間。それらは当たり前ではなく、実は小さな“キセキ”なのです」
「ここで、私たちにできることを一緒に考えてみましょう。まずは “あるもの” への感謝。そしてそれをどう活かせるかを考えること。さらにそれを他者と分かち合う行動をすること。誰かに親切にすることや、自分の得意を活かして誰かを助けること、そうした行動の積み重ねが奇跡の連鎖を生み出し、自分自身にも新たな可能性を与えてくれるのではないでしょうか?」
「特別なことだけが “奇跡” ではありません。“奇跡” は私たちの日常にすでに存在しています。それにまず気づくこと、さらにはそれを分かち合うことが、私たち自身の未来を変える力になります。【今、ここにあるキセキ】を見つけるために、みなさんも小さな一歩を踏み出してみませんか?」
====================================
会場に集った人たち全員が、心に確実な温かなナニカを持ち帰れた冬の始まり。アクセサリー販売や、チュニジア料理の販売なども行われ、菊地ゼミの学生さんたちの頑張りが見えた1日となりました。イベントを企画してくれた菊地ゼミのみなさん、どうもありがとうございました。