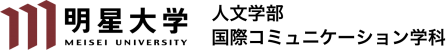学科は、学生さんたちに提供する学びの内容を、常に時代に合わせてアップデートしていくために、随時、教員&有志の学生さんたちも引き連れた勉強会を行っています。
先日は『大人の遠足・多文化共創への学び』をテーマに、1.在留外国人支援センター 2.武蔵野市国際交流協会 3.日野市国際交流協会を訪問しました。

日本の少子化に伴い、日本では一年間に3-40万人という単位で、在留外国人が増加していっています。この単位は、ともすれば、多摩市が2つできてしまうくらいの規模感。1年に流入する外国人の数だけで、『市が2つ』できてしまうような環境に私たちは暮らしているわけですから、これからは『隣の在留外国人』とともに社会を一緒に創っていく、そんな人材が必要とされる時代になってゆくことを予感した教員たちによって、この大人の遠足は実施されました。

まずは四谷駅前のタワービルにある、法務省管轄の在留外国人支援センターを訪問。2020年にできたこの施設では、在留資格の手続きから外国人向けのハローワークの窓口などで在留外国人の相談を請け負っており、日本に住む外国人が安心して生活し、働ける環境を整えることを目的に、ワンストップでさまざまな相談に乗れるようになっています。入国管理局、法務省の人権擁護局、厚生労働省、外務省、経産省、警察庁、技能実習機構、日本貿易振興機構の8つの関係機関がセンターには入っているので、相談者はこの場所に来るだけで在日本での生活面から手続きまでの横断的な相談に乗ってもらうことができます。
今回は内部を見学させていただき、施設についてのさまざまな機能の説明をしていただきました。将来的に『外国人支援コーディネーター』を目指したいという学生も参加、その内容についても詳しく教えてもらいました。


次に訪問したのは、草の根由来の武蔵野市国際交流協会。武蔵野市は古くから国際交流活動が盛んに行われているエリアで、在留外国人の子供たちの学習支援から、さまざまな国際交流イベントなどが行われています。「基本は “国籍” ではなく “その人個人” を見るんです。そうすることで、人としてのシンプルな交流を深めることができ、彼らも日本の暮らしの中に自然に溶け込んでいくことができます」。大学生の往来が多い国際交流協会では、常に人材を欲しているとのことで、学科としても地域貢献、実地演習を踏まえ、多文化共創ジャンルに興味がある学生たちとの、互いにとっての学びが深まる絡みを何か作ることができないかを検討。その後日野市国際交流協会も訪ね、活動内容や現在の状況をお聞きし、大学生がお手伝いできることが何かないかなどをお話させていただきました。
今後ますます拡大していく&コーディネート人材が必要とされるだろう、日本の多文化共創社会。国内での “隣の” 異文化交流に興味がある人は、ぜひ、学科のオープンキャンパスに詳しい話を聞きにきてくださいね。